2 0 1 3 年 8 月
《 17日 〜 18日 》 天上小屋山 ・ 生木割山 ・ 偃松尾山 ・ 笊ケ岳
新倉(ヘリポート) 〜 転付峠 〜 天上小屋山 〜 生木割山(テント泊) 〜 笊ケ岳 〜 偃松尾山 〜 転付峠 〜 新倉 (往復)
笊ケ岳の隣にある白くガレた偃松尾山(2545m)は以前から気になっていた山だが、麓から直接登る道もなく、これまで登る機会を逸していた。 新倉から転付峠に至る登山道は台風の被害でしばらく通行止めになっていたが、まだ荒れてはいるものの、登山道の一部が付け変わったことで通行出来るようなので、ベストシーズンではないが、この機会に静かな山を求めて行ってみることにした。 ルートは雨畑と新倉の両登山口を縦走することも可能だが、この時期ならではの水のボッカと車の回収の煩雑さを考えて、新倉から転付峠を経由して往復することにした。 新倉から転付峠に登るのは今回で3度目となるが、いつでもこのルートは静かで、峠の直下にある涸れることのない水場の記憶だけは新しい。 オアシスのようなこの水場は、盛夏の時期には本当にありがたい存在だ。 麓の早川町のテニスコートの駐車場で前泊し、翌朝そこから車で20分ほど先の登山口に向かう。 以前の広河原の登山口へ通じるコンクリート敷きの車道は台風の被害で2キロほど手前のヘリポートで通行止めになっていて、その手前に広い駐車場があった。 車は他に3台停まっていたが、釣り人もいるので入山者の有無は不明だ。 5時半にヘリポート脇の駐車場を出発。 ヘリポートの標高はまだ700m足らずだ。 やや急勾配の車道をゆっくり40分近く登ると転付峠を示す新しい道標があり、それに従って田代第二発電所方面に左折して橋を渡る。 ヘリポートからここまでの標高差は250mだった。 発電所の上へ雑草に覆われた荒れた林道を緩やかに登っていくと河原に出た。 飛び石伝いに沢を渡り、新しい青い矢印に導かれて沢の右岸を数100m歩いてから再び沢を渡り返した先の急峻な尾根に取り付く。 新しい登山道は一旦廃道となった昔の作業道を復活させたようで、所々にその面影が残っていた。 標高差で200mほど新しい黄色のワイヤーロープがベタ張りされた急峻な尾根を登っていくと朽ちた廃屋の残骸があり、その先の河原まで100mほど下って沢を渡ると、以前の広河原からの登山道と合流した。 冷たい沢の水で体を冷やし、朝食を食べて一息入れる。 沢沿いの登山道は勾配も緩く、合流地点から30分ほどで転付峠への中間点となる東電の保利沢小屋に着いた。 保利沢小屋からさらに沢沿いに登っていくと、再び台風の被害で登山道が荒れている所があり、先ほどと同じ黄色のワイヤーロープが張られていた。 今日初めてすれ違った方は雨畑からの縦走者で、しばし情報交換する。 その後転付峠までの間で延べ5人の方とすれ違った。 登山道が沢から離れると、樹林帯の斜面を緩やかに大きくジグザグを切って登る峠道となった。 カラマツの木々の背は高く、陽射しを遮ってくれるのがありがたい。 予定よりも少し早く10時半前に待望の水場に着いた。 昨今の水不足とは無縁に鮮烈な清水が上下20mほどの間隔を置いて2か所から勢いよく管から出ている。 上の水場は昔の作業小屋の跡地で、テント2〜3張りのスペースがある。 オアシスのような水場でゆっくり寛ぐのも今回の目的の一つだったので、タオルで体の隅々まで拭いたりしながら30分以上休んでクールダウンする。 今日これからと明日のここまでの行動用に2人で7リッターの水をボッカすることにしたが、今回は妻が頑張って3リッターをボッカしてくれたので楽だった。 水場から10分ほどで転付峠(1990m)に上がると、笹山方面から笊ケ岳方面へ縦走中の男女の3人パーティーと出会った。 これから向かう笊ケ岳方面とは逆の方向に展望台があり、峠に荷物を置いて5分ほど歩いた先の展望台に立ち寄る。 展望台も良い幕場になっていて、眼前には千枚岳と悪沢岳が大きく望まれた。 水場や展望台で1時間以上まったり過ごしてしまったが、11時半過ぎに転付峠を発って笊ケ岳方面への縦走路に入る。 荒れた林道をしばらく進むと、1週間ほどかけて北岳から大縦走(周回)してきたという猛者とすれ違ったが、その後は下山するまで新たに出会った人はいなかった。 転付峠から笊ケ岳方面へは7年前の秋に蝙蝠岳を登った時に、二軒小屋からの帰路に天上小屋山(2350m)まで行ったが、天上小屋山から笊ケ岳の間は未踏破だった。 雑草に覆われた林道の終点からひと登りすると、登山道は保利沢山(2379m)の西側斜面を1時間ほど延々とトラバースする巻き道となった。 詰まった木々の隙間から南アルプスのジャイアンツが微かに見える程度で縦走の面白みに欠けるが、昼間でも夏の陽射しが届かず、暑さに苛まれることはなかった。 2000m以上の標高でこれほど長い巻き道は日本では他にないだろう。 地味な天上小屋山の頂が前方に見えるようになると、一か所だけ僅かに木々が切れている所があり、眼前に鎮座する荒川三山を眺めながら一息入れる。 巻き道はその先で終わり、天上小屋山への登りとなる。 山頂の手前には1.5張りほどの広さの幕場があった。 赤石岳とほぼ同じ緯度にある天上小屋山は展望に恵まれない不遇な山だ。 2時前に天上小屋山を通過する。 一番暑くなる時間帯だが、相変らず樹林が濃く展望がないため夏山とは思えない快適さで、ザックの重さもあまり苦にならず歩くことが出来た。 緩やかな登り下りを繰り返し、最後に目的地の生木割山の山頂に向けてひと登りする。 3時ちょうどにケーブルテレビの小さなアンテナが置かれた人待ち顔の生木割山の山頂に着く。 樹林に囲まれた平らな山頂は昔から幕場として親しまれているが、今日はまだ誰もいなかったので、山頂脇の一番平らで良いスペースに幕を張る。 夕方になっても転付峠で出会った男女の3人パーティーは到着しなかったので、図らずも山頂は貸し切りとなった。 山頂は樹林が濃いため素晴しい夕焼けショーは見られなかったが、木々の隙間から夕陽に染まる白峰三山が遠望されたのが嬉しかった。 転付峠からここまで水の消費量が予想よりだいぶ少なかったので、明日は予定してなかった笊ケ岳まで足を延ばすことにした。

広河原の登山口へ通じる車道は台風の被害で2キロほど手前のヘリポートで通行止めになっていた

田代第二発電所の上へと雑草に覆われた荒れた林道を緩やかに登る

新しい青い矢印に導かれて沢の右岸を数100m歩く

標高差で200mほど新しい黄色のワイヤーロープがベタ張りされた急峻な尾根を登る

新しい登山道は廃道となった昔の作業道を復活させたようで、所々にその面影が残っていた

以前の広河原からの登山道との合流点

転付峠への中間点となる東電の保利沢小屋

保利沢小屋の先にも台風の被害で登山道が荒れている所があり、ワイヤーロープが張られてた

登山道が沢から離れると、樹林帯の斜面を緩やかに大きくジグザグを切って登る峠道となった

転付峠の直下にある涸れることのない水場は、鮮烈な清水が勢いよく管から出ていた

上の水場は昔の作業小屋の跡地で、テント2〜3張りのスペースがある

転付峠

転付峠の展望台も良い幕場になっていた

展望台からは眼前に千枚岳と悪沢岳が大きく望まれた

雑草に覆われた林道の終点から保利沢山へ

保利沢山の西側斜面を1時間ほど延々とトラバースする巻き道

天上小屋山の手前の木々の切れ目から見た荒川三山

天上小屋山の手前の木々の切れ目から見た赤石岳

天上小屋山への登り

展望に恵まれない天上小屋山の山頂

天上小屋山から先も樹林が濃く展望がないため夏山とは思えない快適さで歩くことが出来た

ケーブルテレビの小さなアンテナが置かれた人待ち顔の生木割山の山頂

山頂脇の一番平らで良いスペースに幕を張る

木々の隙間から夕陽に染まる白峰三山が遠望された
翌朝は3時半に幕場を出発し、偃松尾山の先の笊ケ岳へ向かう。 登山道は明るければ問題ないが、倒木や獣道が多くヘッドランプの灯りではスピーディーに歩けない。 相変らず樹林が濃く、朝焼けの山々は望めないと思っていたが、運良く木々の隙間から黎明の富士山を拝むことが出来た。 生木割山から1時間ほどでポッカリと空いた偃松尾山のシンボルとも言えるガレ場の淵に飛び出し、その上端の薄い踏み跡を登る。 5分ほどガレ場の淵を登り、笹の切り裂きから再び樹林帯の道に入る。 縦走路から外れている偃松尾山の山頂は帰路に踏むことにして、笊ケ岳との鞍部に向けて急坂を下る。 東の空が明るくなり、5時過ぎに富士山の左の雲海から久々にご来光を拝んだ。 平坦な鞍部で椹島へ下る道を右に分けると、勾配が次第に急になり笊ケ岳への登りとなる。 途中に一か所樹林が切れた所があり、山頂を待たずに朝陽を浴びた淡い南アルプスのジャイアンツが望まれた。 雲一つない快晴の天気に足取りは軽い。 登山道を覆う朝露で濡れたシャクナゲをストックで叩きながら進んでいくと周囲が明るく開け、5時半過ぎに19年ぶりとなる懐かしい笊ケ岳の山頂に着いた。 猫の額ほどの狭い山頂のハイマツが成長し、眼前の山々の展望を遮っていたが、山頂の北側の露岩からは遥か眼下の大井川の源流から稜線まで遮るものない大展望が得られた。 誰もいない静かな山頂に1時間ほど滞在し、北は鳳凰三山から南は深南部の黒法師まで、南アルプスの山々の大展望を十二分に堪能することが出来た。 いつまでも去りがたい山頂を辞し、まだ未踏の偃松尾山に向かう。 鞍部から登り返した所で、昨日転付峠で出会った男女の3人パーティーとすれ違った。 偃松尾山は南アルプスの主脈から南嶺を眺めた時に笊ケ岳の左に見える山肌が白くガレた山だ。 2500mを超える山だが、山頂の写真は見たこともない寂峰だ。 縦走路から外れた山頂方面に導く道標やテープの類は一切なく、這い松の切り裂きから微かな踏み跡を辿っていく。 すぐに三角点があったが、その先で踏み跡は消え、山名どおり這い松の密藪となった。 這い松を掻き分けたり、上に乗ったりしながら指呼の間のピークを目指すが、深雪のラッセル以上に前に進まない。 飲み水にも余裕がないので、ピークまで行くことは断念したが、 標高はせいぜい10mほどしか変わらないので、見える景色はそう変わらないだろう。 山頂直下のガレ場の淵からは往路では暗くて見えなかった笊ケ岳が大きく望まれた。 8時半に生木割山に戻り、テントを撤収してもう訪れることはない山頂を後にする。 昨日同様、転付峠まで展望はないが暑さもない地味な道を緩やかに下った。 転付峠の下の水場では往路と同じようにゆっくりと寛ぎ、誰とも出会うことなく4時半に車を停めたヘリポートに戻った。

3時半に幕場を出発する

登山道は倒木や獣道が多くヘッドランプの灯りではスピーディーに歩けない

木々の隙間から黎明の富士山を拝む

富士山の左の雲海から久々にご来光を拝んだ

笊ケ岳の山頂手前の樹林が切れた所から見た朝陽を浴びた淡い赤石岳
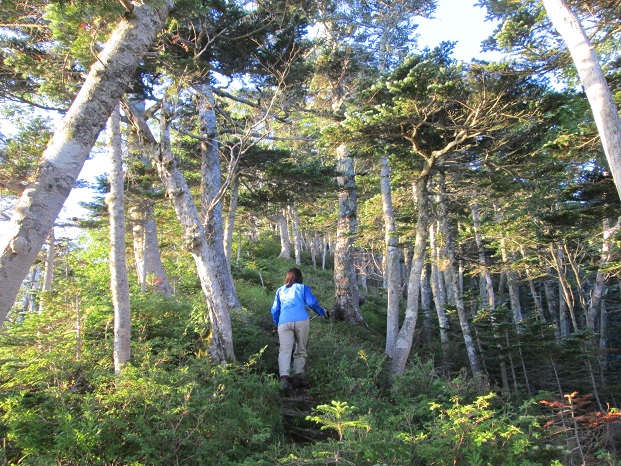
笊ケ岳の山頂への最後の登り

笊ケ岳の山頂

山頂から見た偃松尾山(右手前) ・ 生木割山(左手前) ・ 白峰三山(右奥) ・ 塩見岳(左奥)

山頂から見た布引山

山頂から見た小笊

山頂から見た赤石岳(左) ・ 荒川岳(右)

山頂から見た聖岳(左) ・ 赤石岳(右)

山頂から見た上河内岳(左) ・ 聖岳(右)

山頂から見た聖岳(左) ・ 赤石岳(中) ・ 荒川岳(右)

山頂から見た白峰三山(左奥) ・ 鳳凰三山(右奥)

偃松尾山の山頂直下から見た生木割山

偃松尾山の山頂直下のガレ場の淵から見た笊ケ岳

偃松尾山の山頂直下のガレ場の淵から見た生木割山

樹間の詰まった偃松尾山から生木割山への縦走路

生木割山から天上小屋山へは展望に恵まれない地味な道を歩く

天上小屋山の先の木々の切れ目から見た赤石岳(左) ・ 荒川岳(右)

天上小屋山の手前の木々の切れ目から見た塩見岳
